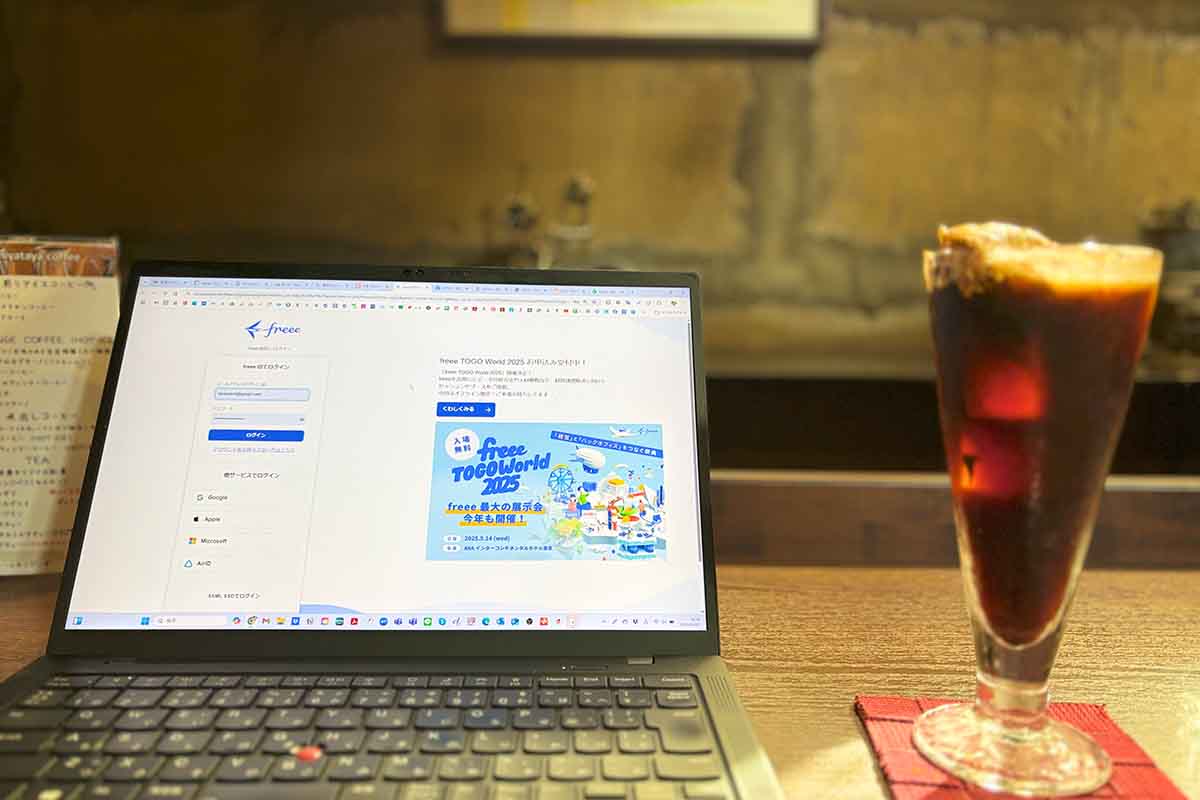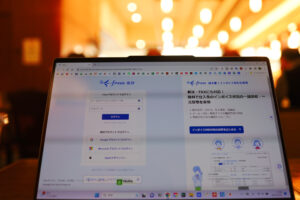決算の実績と比較される着地見込み。
その精度をどこまで気にするか。だいたいくらいで考えておきましょう。
決算の「着地見込み」とは
決算の着地見込み。
「決算予測」とも言われています。
決算を迎える前に、利益がどれくらい出そうかを予測します。
予測にすぎないので、正確性は二の次です。
予測は正確性よりも適時性。
正確性を気にしすぎると、予測できないまま決算を迎えてしまうことすらあります。
今より先を見た行動につなげるためには、
・できる節税をする
・お金を借りておく
・売上や経費の処理上の判断
といった前持っての行動が必要です。
見込みの精度は毎月の経理が前提
ここでいう「着地見込み」や「予測」というのは、中長期計画のような期間の長いものではありません。
年間の見込みや予測です。
「年間」といっても、最初の1か月分が実績で、残りの11か月が予測という意味でもありません。
予測するのは、せいぜい残り3カ月~1か月分です。
6月決算だと、期首の7月~3月の経理はすんでいて、その9か月分の実績に、残りの4月~6月分を予測する合計するイメージです。
毎月の経理がどれくらいできているかによって、見込みの精度も変わります。
売上は少なめに、経費は多めに
予測をたてるときは、「売上の予測」-「経費の予測」で計算します。
それを差し引きしたのが「予測の利益(着地見込み)」です。
予測は、前月までを参考にしたり、前年を参考にしたり、平均値を使うなどいろいろあります。
売上は予測できるものを入れておきましょう。
ただ、ここで注意しておきたいのは、
・甘く見ない
・できるだけ厳しめに
ということです。
売上は少なめに、経費は多めに。
多少厳しめくらいに見ておくようにしましょう。
なんだかんだ言っても見積りです。
実際にその月になってみたら、当初の見積りと違ったというのはありえます。
・売上を多めに予測していた→実際の売上はそれより少なかった→利益が予測より少なかった
・経費を少なく予測していた→実際の経費はそれより多くかかった→利益が予測より少なかった
となっては、受けるダメージも大きくなります。
なんだかんだ言って、リスクを多めに見ておくほうが、人間、安心できるものです。
逆に想定していないリスクを受けるほど、ダメージは大きくなるものです。